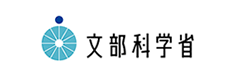公募研究(2021〜2022年度)
A01班
シカン遺跡大広場の発掘と景観分析(山形大学・松本剛)
本研究の目的は、これまで「何もない空間」という誤った仮定から考古学研究の対象となることがほとんどなかった広場という公共空間に焦点をあて、そこでの人間行動の多様性とその変遷を詳細に研究することにある。研究対象は、今から約千年前にペルー北海岸で栄えたシカン政体最大の祭祀センター(シカン遺跡)の中心に位置する大広場である。松本はこれまで大広場を、これに隣接するピラミッド型神殿基壇で行われた祖先信仰との関連において論じてきた。しかし、近年の発掘調査がもたらした新たな発見によって、この空間は祖先信仰というキーワードだけでは説明しきれない多様さを持っている可能性が明らかになった。そこで本研究では、大広場の発掘を完了させることによって、その儀礼空間としてのはじまりを明らかにするとともに、その多様性を読み解きたい。これによって、広場とその周囲のモニュメント群を景観という一連なりのコンテクストの中で論じる。
メソアメリカにおける都市空間の創成(名古屋大学・伊藤伸幸)
ヒトが住み始める前の自然景観の復元を基として、どの自然環境のニッチを先古典期のメソアメリカの人々が選択したのかを解明する。そして、モニュメンタルな建造物や石彫などが追加されて、どのように都市景観が形成されたのかを探究する。
メソアメリカ南東部太平洋側の重要遺跡チャルチュアパは、先古典期前期に居住が始まり、先古典期中期にエルサルバドル最大の建造物E3-1が建設された。建設以前の原風景を、当該遺跡とその周辺の考古学調査で得られる層位学的な資料と自然地理学的調査の情報を基に復元する。一方、先古典期中後期にこの遺跡の中心となったエル・トラピチェ地区において、E3-1建造物前庭部の発掘によって、聖なる空間と俗なる空間の発展段階を追求してきた。本研究では、都市空間の創成の様相を探るため、E3-1建造物を発掘し、モニュメンタルな建造物の建設と都市空間の創成との関係を考察する。
最後に、先古典期前期から先古典期後期に至る、チャルチュアパ遺跡における都市景観変遷の復元を試みる。
A02班
古代メキシコの都市化の原理:物質性と物質化による宇宙を含めた空間支配の復元(京都外国語大学・嘉幡茂)
本研究の目的は、認知考古学の視点から、古代メソアメリカ文明における都市の萌芽と発展を解明することにある。物質性(Materiality)と物質化(Materialization)を基にした空間支配(空間の取り込み)の確立と拡大が、都市の興隆に必要不可欠であったとの仮説を検証する。都市は物質的な豊かさが基盤にあると考えられている。一方、古代メソアメリカ文明における都市の本質は、社会的紐帯をより大規模に可能にさせた象徴空間にあるとの観点から研究を行う。物質的側面に認められる豊かさは、社会的紐帯の成功がカギとなっている。さらに、社会的紐帯の成功は、自然景観に存在する各要素(水や山など)に物質性を付与し、それを都市に取り込む行為(物質化)にあったと考える。古代メソアメリカでは、自然景観の各要素に神々が宿り、彼らから超自然の力を獲得することで社会秩序の安定が約束された。本研究では、都市萌芽の原動力と発展過程は、古代人の認知体系の発達とその物質化に関係するとの仮説の下、考察を深める。
A03班
偏狭な利他主義仮説の実証的検討(北海道大学・高橋伸幸)
何世紀にもわたり、人間の本性は利他的か否かという問いは論争の対象となってきたが、21世紀に入り、人間の利他性は外集団に対する攻撃性と不可分であるとする「偏狭な利他主義仮説」が提唱された(Bowles and Gintis, 2010)。この仮説は、集団内での利他行動と外集団に対する攻撃という二つの行動は共進化したと主張する。もしこの仮説が正しいのであれば、人間の利他性を引き出すような政策は、必然的に外集団に対する攻撃行動をも促進してしまうことになるため、この仮説の妥当性を検証することは、学問的意義も実社会に与える影響も極めて大きい。しかし、これまでこの仮説を支持するとされていた研究も、支持しないとされていた研究も、その研究方法に様々な問題点を抱えている。そこで本研究では、新たに開発した集団間先制攻撃ゲームを用いて、世界ではじめて偏狭な利他主義仮説を厳密に検証する。
マヤ文明黎明期の複合社会の形成と戦争に関する研究(茨城大学・青山和夫)
マヤ文明黎明期(前1200〜前700年)最大のアグアダ・フェニックス遺跡(メキシコ)とウスマシンタ川中流域の近隣諸遺跡で、支配層と被支配層が製作、流通、消費した武器や様々な遺物の時間・空間分布及びモニュメント建築の出現と変容を詳細に分析し、まだ十分に解明されていないマヤ文明黎明期の社会の複合化と戦争に関する比較考古学データを提供する。石器の機能を明らかにするために高倍率の金属顕微鏡を用いて石槍(両面調整尖頭器)など武器と考えられる黒曜石・チャート製石器や他の石器の使用痕を分析し、武器の時間・空間分布を検証する。その他の戦争の証拠として、?防御遺構、?戦争に関する図像、?殺傷痕のある人骨、?建造物の破壊、?都市・集落の破壊と短期間の放棄、?急激な文化変化(外来の土器様式や美術様式の導入など)についても検討する。さらにハンドヘルド蛍光X線分析計による先古典期前期(前1200〜前1000年)の黒曜石製石器の産地同定という分析手法を世界で初めて導入して、メキシコ高地・グアテマラ高地産黒曜石の遠距離交換の通時的な変化を検証する。
古代マヤ王族の日常的実践から解明する戦争と階層化の関係性(京都外国語大学・塚本憲一郎)
本研究の目的は、パフォーマンス理論と実践理論を視座に、メキシコのマヤ遺跡、エル・パルマールの王宮を平面的・層位的に発掘して、古代社会における戦争と階層化(不平等の制度化)の関係性を解明することである。これまで古代マヤ王朝における戦争と階層化の研究は、自然環境変化、碑文や威信財の交換から解釈する王朝間交流といったマクロ的視座に依拠してきた。しかし、日々の実践が大きな社会変化を引き起こすという事実は、歴史民族学や社会学調査によって実証されている。本研究は、マクロ的視座を取り入れながらも、王族の日々の生活というミクロ的視座に着目し、戦争や階層化が日常化し、文化的に取り入れられていく過程を考察する。本研究では、発掘に加えて、地中レーダー探索、出土遺物の肉眼・顕微鏡分析と理化学分析、碑文解読、放射性炭素年代測定とベイズ統計に基づいた高精度編年の確立による総合的アプローチから、マヤ王族の諸活動を復元する。
B01班
「草原の掟」としての伝統知が果たす遊牧コミュニティの持続機能の解明 (筑波大学・相馬拓也)
本研究は、モンゴル西北部〜南部の草原地帯に暮らす遊牧社会において、伝統知「草原の掟」の継承・実践が、防災・減災・災害対処などコミュニティの持続性/レジリエンスに果たした役割を解明する。モンゴルに代表される遊牧社会では、防災・減災術・災害対処・家畜防衛・環境適応・在来資源利用などに関する伝統知が、口承伝達・語り・掟などの社会規範化した生活実践として継承された。そのため、本研究では伝統知/在来知を「非文字的コミュニケーションにもとづく文明形成の知的資源」として再評価する。研究実務は、定量社会調査 (T1)、リモートセンシング調査 (T2)、社会ネットワーク調査 (T3)を課題とし、合計80日間のフィールド調査(第?期〜第?期)および、コンピューターワークにより遂行する。伝統知の研究に科学的エビデンスを統合した学知融合の新しい研究モデルを提案する。
リモートオセアニアへの拡散を可能にした栄養適応システムの解明(東京大学・梅崎昌裕)
リモートオセアニアへ人類が拡散するプロセスで、エネルギー・栄養素の不足、あるいは食品に含まれる毒性物質の影響を緩和するために、腸内細菌が果たした役割を解明することを目的とする。現代の技術では、先史人類の腸内細菌を調べることは技術的に難しいので、リモートオセアニアに居住する現生人類のなかで、生活の近代化のレベルの異なる集団を対象に糞便をサンプリングし、より「伝統的な」生活をおくる人類集団において相対的におおくみられる腸内細菌リストを作成することを第1の到達目標とする。これらの細菌リストは、リモートオセアニアに人類が拡散したプロセスにおける生存戦略に寄与した可能性のあるものであり、メタゲノム解析による機能遺伝子の情報とあわせて考えることにより、リモートオセアニアへの人類の拡散における人類の生存戦略についての新たな仮説を提示したい。
アメリカ大陸極北圏での人類の認知技能の発達に関する民族認知考古学的研究(放送大学・大村敬一)
本研究の目的は、?アメリカ大陸極北圏と亜極北圏の現在の先住諸民族の生業システム(生業技術と社会組織と世界観から複合的に構成される物質=観念的な社会・経済・文化システム)を分析し、そのシステムの環境適応のメカニズムとそれを支える認知技能を明らかにするとともに、?その生業システムの歴史を考古学的に辿ることで、アメリカ大陸に進出した人類にどのような認知技能の発達が生じたのかを探究することである。その際に、本研究では、身体と技術を媒介とした認知と環境の相互作用が、生業システムの歴史的な発達で果たした役割にとくに焦点をあてることで、北方寒冷地適応と認知技能の発達の関係についての仮説を提示する。そのために、本研究では、民族誌学者と考古学者が緊密な連携と共同を行い、生業システムのメカニズムとその歴史的展開、さらに、そこでの北方寒冷地適応と認知技能の発達の関係に関する調査研究を推進する。
ペルー北部山村の自然観と環境開発をめぐる人類学的研究−感情マッピングによる分析(立命館大学衣笠総合研究機構・古川勇気)
本研究は、「出ユーラシア」後にアンデス山村で育まれた「景観」による信仰体系やコスモロジーに基づいて、現地住民の開発実践に対する感情の濃淡をマッピングすることで、今日的な環境開発の実践を社会的文脈に即して再考するものである。
地球温暖化による水不足は、地球規模で解決すべき契緊の問題である。南米のアンデス山脈では、 温暖化によって過去35年間に約22%の氷河が減少し、深刻な水不足が起きている。そのため、アンデス農村では近代的な灌漑事業が展開されているが、多くの場合、住民による反発や逃散を招いている。本研究では、ペルー北部カハマルカ県山村の環境開発に対して「反発」と「融通」のあいだで揺れ動く感情的な濃淡を、川、湖、池、丘などの景観の信仰実践、民話・逸話と日常的な環境利用に着目してマッピングする ことで、当事者の実践や関係、問題系が矛盾をはらみつつもミクロに調整されていく過程を明らかにする。
B02班
民族移動のボトルネック経過後の食物、環境の変化による顔面形成の共進化について(岡山大学・上岡寛)
脳の生後発達による脳頭蓋底の骨形態変化は、顔面骨の成長形成に関連する。この点に着目し、アジア大陸から海を越えてインド洋の孤島に渡るというボトルネックを経て、特異的に道具使用による採餌行動を獲得したタイ沿岸島嶼のマカク猿と、本土で生活し、道具を使用しない同種のマカク猿をモデルとして、後天的な認知行動獲得に伴う頭蓋骨・顔面骨の発達変化を解析し、ヒト進化過程における食物・環境の変化と民族特有の顔面形成の共進化について検討する。そのために、歯科矯正学分野で確立している頭蓋・顔面の臨床的評価方法を応用して、認知科学班の研究リソースを共同利用すると同時に、岡山大学病院で長年培ってきたミャンマーとの国際協力体制を活用することで、調査地域をタイ王国からさらに多くのマカク猿が棲息するミャンマーの孤島に広げることにも貢献する。そして、人類の進化における民族特有の顔貌形成のメカニズムを解明する基盤を築きたい。
B03班
出ユーラシアを支えた寒冷適応の遺伝的基盤の解明(東京大学・中山一大)
ヒトのアメリカ大陸への進出には、寒冷気候への生物学的適応が重要な役割を果たしたと考えられている。亜北極地域の先住民を対象とした進化遺伝学研究から、適応進化を遂げた可能性が高いゲノム領域がいくつか報告されているが、その生理的意義は不明である。東アジアは南北アメリカ大陸への進出の中継地点の一つとして捉えることができ、亜北極圏の先住民集団で自然選択によって固定された遺伝的バリアントのなかには、東アジア人集団ではいまだに多型的なものが数多く存在しており、遺伝型と表現型の関連性を検証することが可能である。本課題では、日本人成人の複数の集団に対して各種の生理実験とゲノムDNAの収集を実施し、亜北極圏周辺のヒトの集団で自然選択を受けたことが報告されているゲノム多型と熱産生形質との関連を検証することにより、出ユーラシアを支えた寒冷環境への遺伝的適応の実態に迫る。
自然環境と文明の変遷に伴う選択圧の変動:古代・現代マヤの集団ゲノムモデリング(金沢大学・中込滋樹)
私たちの研究チームでは、古代及び現代ネイティブアメリカンのゲノムデータを用いた集団遺伝学解析から、自然環境の変化や文明の変遷に伴う選択圧の変動と現代人におけるその影響を明らかにします。ネイティブアメリカンの祖先は、ユーラシア大陸からアメリカ大陸へと拡散する過程で様々な環境にさらされ、それらが新たな選択圧として適応進化を引き起こしてきました。しかし、自然環境だけが進化を駆動したわけではありません。15世紀に始まったヨーロッパ人の大規模なアメリカ大陸への移住・植民地化によって、感染症がネイティブアメリカンに拡がりました。本研究では、『自然環境に起因する選択圧』と『文明の変遷に伴う選択圧』がネイティブアメリカンの進化を促してきた歴史を辿ります。
アジア太平洋地域におけるヒト皮膚形質の環境適応(琉球大学・木村亮介)
ヒトが拡散する過程で、新天地における紫外線量、温度、湿度といった物理環境およびそれに依存する微生物環境にヒトの皮膚は適応してきたと考えられる。ヒトゲノム多様性情報からアジアにおいて強い自然選択の痕跡が示されたABCC11 Gly180ArgとEDAR Val370Alaの二つの多型が共に皮膚機能と関連することは興味深く、アジアにおける気候が関係していることが示唆される。さらに、古代人類から受け継いだアリルが現生人類において正の自然選択を受けた痕跡がケラチン繊維形成に関係する遺伝子群に集積していることや、皮膚で高発現するPou2F3の周辺配列にみられることも報告されている。本研究では、皮膚機能に関連する遺伝子に注目しながら、現生人類および古代人類のゲノム情報から特にアジア太平洋地域集団において自然選択が働いた多型を抽出し、細菌叢を含む皮膚形質との関連を明らかにする。また、出ユーラシア集団も含め皮膚形質関連遺伝子多型の分布を調べ、多型の起源を推定しながら、各地域における気候や文化を勘案して適応過程について考察を加える。
反復多型より探る環境適応における多様性の役割(藤田医科大学・嶋田誠)
現代人類の生息域拡大と人口増加は、多くの多様な構成員から成る分業社会構築能力の獲得によるところが大きい。分業社会は集団内での脳・神経系活動の多様性により生まれたと考え、グルタミン反復数の多型に着目している。かつて我々はヒトゲノム中の全グルタミン反復のうち反復多型のある座位にのみ、神経発達調節に関わる遺伝子領域中に有意に多く存在する傾向を見出した。神経発達過程において、生じる神経突起数の違いや特定の脳領域 (淡蒼球) の灰白質量の違いに、グルタミン反復数が関連することが知られ、しかも類人猿との分岐以降、グルタミン病発症リスクが生じたにもかかわらず、多型が多様化した。その謎を解明するため、世界中の人類集団におけるグルタミン反復多型の分布状態を、新技術によって明らかにし、その頻度変化の解析により、ヒトの性格や行動の多様性が、地球上に増え広がる過程で如何に生じ、維持されてきたかを解明する。
ヒトはなぜ戦うのか−生物考古学的資料に基づくアンデス文明形成史の解明−(青森公立大学・長岡朋人)
発掘人骨に残された外傷の痕跡は,古代人の唯一かつ直接の暴力の証拠である。アンデス文明は1532年にインカ帝国が滅びるまで国家の興亡が繰り返しみられ,暴力や戦争と密接にかかわりながら発展してきた(Fig. 1)。本研究では,アンデス文明の遺跡からの発掘人骨に残された外傷の痕跡を手がかりに,「儀礼的な犠牲」と「組織的な闘争」,二種の暴力から見た文明史を構築する。具体的な課題は,(1)発掘人骨に残された外傷はどのような所見(種類,頻度,好発部位,重症度,治癒痕)を持ち暴力の結果と見る証拠はあるか,(2)犠牲者の生老病死はどのようなものであったか,(3)古代アンデスにおいて暴力と戦争はいつから始まり,社会的・経済的・環境的要因によってどのように変化したか,である。生物考古学は,骨に残された病気や生活痕の断片をつなぎ合わせることによって,過去を生きた古代人そのものから個体が生を受けて死ぬまでのプロセスを精緻に復元できる独創性がある。
Fig.1.Example of violence-related trauma in the Late Cajamarca Period in Pacopampa in the northern highlands of Peru. (a) Depressed skull fracture in the right parietal bone (specimen No. 13PC-G-Ent 01), (b) a magnification of the fracture from the superior view, and (c) a magnification of the fracture from the inferior view (Tomohito Nagaoka, Yuji Seki, Mauro Ordoñez Livia, Daniel Morales Chocano, Depressed skull fracture at Pacopampa in the Peru’s northern highlands in the Late Cajamarca Period. Anthropological Science, 2020, accepted). ©Pacopampa Archaeological Project
C01班
ヒトの拡散過程の比較生物学的分析(早稲田大学・中橋渉)
人類、特にホモ・サピエンスの拡散については、しばしば、さもそれが特別にすごいことであったかのように表現される。そして本研究領域で着目されている「文化的ニッチ構築」や、あるいは「好奇心」や「冒険心」といった要素がそれに大きく寄与したかのように何の科学的根拠もなく語られる。しかしヒトの分布域拡大は、ヒト独自の何かを持ち出さなければ本当に説明できないのであろうか。実際に他の多くの生物も様々に分布域を広げており、それらと比べてヒトの拡散が本当に特別な現象だったのかは注意深く検証されなければならない。そこで本研究課題では、ヒトの拡散過程を他の生物、特にデータの豊富な侵入生物の拡散過程と数理モデルを用いて比較する。それによって、ヒトの拡散過程に影響したヒト特有の要素は存在したのか、そしてもし存在したならそれは何で、その影響はどの程度だったのかを科学的に検討する。
3D石器形態系統分類学による日本列島およびサフル大陸における人類進出の解明(奈良文化財研究所・野口淳)
本研究は、3D 計測による石器形態研究によって先史時代人類集団の動態復元のための考古学的方法論の確率を目的とする。3D 計測による〈かたち〉、形態の定量化情報から、技術的・機能的属性を検討し、石器形態形成過程にもとづく系統分類を行なう。主要な検討対象は、中期〜後期旧石器時代の日本列島とサフル大陸の、刃部磨製石斧を含む礫器である。 注目するのは、ユーラシア南東縁に沿って、無人ないし人口希薄だった日本列島とサフル大陸に進出した人類集団に、どのような技術、行動、文化的変化が起こったのか、その背景はどのようなものであったのか―例えば原集団から分岐した後の系統的変化か、あるいは類似環境下での特定の道具の収斂進化なのか―である。そのために、石器の完成(廃棄)形態のみを基準とした分類、その差異・類似を集団の表象とする従来の考古学的分類法の限界を克服し、適応行動と文化的選択を識別する新しい方法論の確立を目指す。これは現代型人類の世界拡散過程中でも特筆すべきイベントである最初の「出ユーラシア」を議論するための考古学の方法論的基盤の提示でもある。