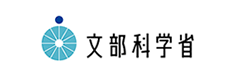公募研究(2022〜2023年度)
A02班
北海道の旧石器時代から縄文時代にかけての石製装身具の変容に関する総合的研究(北海道大学・高倉純)
玉や垂飾などの装身具は、社会的アイデンティティやネットワークを表示するメディアとなっていた可能性があり、先史時代の社会システムやコミュニケーションの進化を復元するための重要な手がかりを提供してくれる。北海道の旧石器時代には、最終氷期最寒冷期に、北アジアからの細石刃技術を伴ったホモ・サピエンス集団の拡散によって、石製装身具がもたらされている。本研究の目的は、北海道がユーラシア大陸に連なる環境から島嶼的環境に変容し、人類集団の行動パターンが遊動的なものから定着的なものに移り変わっていく過程のなかで、そうした石製装身具が、社会システムやコミュニケーションの変化をどのように反映しているのかを解明していくことにある。そのために本研究では、旧石器時代の遺跡から石製装身具の新資料を獲得するための調査を実施するとともに、既出土資料の岩石学的分析ならびに製作・使用過程に関する微細痕跡分析に取り組むことによって、旧石器時代から縄文時代初頭にかけての石製装身具の変化の体系的把握を目指していく。
笛吹きボトルの構造研究と音響解析から探る古代アンデスの水にかかわる世界観(東海大学・吉田晃章)
古代アンデスの笛吹ボトルに関する研究は、出土例が多いエクアドルにおいて、使用法や意味論的解釈、形態変化などがテーマに行われてきた。笛吹ボトルとは、ホイッスル(笛玉)を備え、土器内部で水と空気が移動するときに音が鳴る、内部構造が比較的複雑な土器である。笛吹ボトルの用途として葬儀、儀式、祝祭との関連が示唆されてきたが、笛吹ボトルに関する科学分析を行った既存の研究は数少ない。さらにエクアドルではなく、ペルーの各文化における笛吹ボトルの種類、使用方法、土器で音を鳴らすことの意味など分からないことが多く、体系的な研究もなされていない。そこで研究協力者とともに、ペルーの笛吹ボトルのX線CT 撮影を行い、欠陥解析などから成形と構造について研究を実施する。研究対象の遺物は、東海大学文明研究所が所蔵するアンデス・コレクションである。STL データから3D レプリカの作成を行い、レプリカに水を入れて音を鳴らし、音の解析から文化ごとの、あるいはボトルのタイプごとの音の特徴を把握し、「聴覚」という観点から当時のアンデスの人々の音に対する趣向や心性に迫りたい。
アンデス文明における土器製作の創発プロセス:境界領域の事例をもとに(東京大学・金崎由布子)
本研究は、アンデス文明形成期における土器出現から二千年間の土器製作システムの創発プロセスを明らかにするものである。アンデス文明の初期の土器には、土器製作が先行するアマゾン地域の影響が見られ、アンデス・アマゾン間の境界領域はアンデス文明の土器製作技術の発達に重要な役割を果たしたと考えられる。筆者はこれまで、山地・熱帯の境界付近に位置するワヌコ盆地の研究を行い、土器の出現から千年間の変化の詳細を明らかにしてきた。これにより、当地域では周辺の山岳地帯、熱帯低地の双方との関係のもとで、土器スタイルが急激に変化していく様子が明らかになった。 そこで本研究では、境界領域の流動的な社会状況のもとで、土器製作者のスキル、アイデンティティ、社会的立場がどのように歴史的に形成されていったのかに焦点を当て、ワヤガ・ウカヤリ川流域の事例をもとに、文明形成期の土器製作システムの創発プロセスを明らかにする。
湖畔の考古学:古代メキシコにおける水のシンボリズムと表象内容の多様性(京都外国語大学・嘉幡茂)
本研究の目的は、古代メキシコで社会統合の文化要素として機能した水のシンボリズムとその表象内容の多様性に着目し、複雑化社会へと至る従来の見解に新たなデータと知見を示すことにある。研究代表者は、現在までの研究を基に、メソアメリカ考古学界における中心テーマの一つである古代都市の形成・発展の解明に努めてきた。結果、人々が共有できるシンボルの確立が重要であり、水のシンボル化と都市の発展が密接な関係を持つとの結論に至った。水のシンボルは、メソアメリカの様々な自然環境やこれに順応した多様な生業形態の中から、独自の過程を経て地域レベルで誕生していった。異なる起源を持つこれらのシンボルは、社会の発展と交易網の広がりによって徐々に融合し、やがて複数の属性を併せ持つ神として結実したとの仮説を検証する。今まで考慮されなかった湖畔遺跡における水のシンボリズムを理解することで、複雑化社会の過程をより総合的に解明する。水と関連する古代人の物質文化(「アート」)の発生と発展、そして変化を通時的に考察することで、A02班が解明を進める「自然環境を神格化・擬人化するプロセス」に貢献でき、「新たな文化観」を提供できると考える。
A03班
古代マヤ社会における祭祀儀礼と戦争に関する研究(京都外国語大学/カリフォルニア大学リバーサイド校・塚本憲一郎)
本研究は、古代マヤ社会の異なった空間における戦争儀礼を比較して、暴力が身体化・物質化する社会プロセスを解明することを目的とする。古代社会の戦争に関する研究は、戦争の有無、戦術や武具、戦争技術面、政治体制の崩壊などを、中央集権化や社会階層化などといった社会変化と結びつけて研究されてきた。これらの先行研究は社会変化のプロセスを解明する上で重要な成果を挙げた一方で、戦争が生活の一部として浸透し、文化概念として身体化・物質化する過程で形成される社会関係についてはあまり検討されていない。殊に古典期(後250~900年)のマヤ社会において、戦争は個人や社会のアイデンティティーを形成する重要な要素であったが、一般の人々が参加した公共広場における戦争に関連する祭祀儀礼と、支配層のみが参加を許された戦争儀礼では、その特徴が異なっていた。本研究は、メキシコにあるエル・パルマール遺跡の排他的空間を形成していた王宮広場の発掘によって得られるデータを、第一期の公募調査で得た公共広場の資料と比較して、戦争と社会の複合化プロセスを解明する。
B01班
草原世界の伝統知に秘められた人類の生存戦略の探索(東京大学・相馬拓也)
本研究では、モンゴル~キルギス~カザフスタンの草原世界に暮らす遊牧民の伝統知の継承と実践が、草原適応、災害対処、コミュニティ持続性などに果たした役割から、人類史上の生存戦略の意義を探求します。中央ユーラシア草原に代表される遊牧社会では、家畜防衛・災害対処・薬草利用・狩猟・水源・牧草地利用などに関する伝統知が、口承伝達・語り・掟などの社会規範化した生活実践として継承されました。本研究では伝統知を、「非文字的コミュニケーションにもとづく文明形成の知的資源」として再評価できる可能性に注目しました。
前回公募研究により、「草原の伝統知」の継承性と非文字的記録のドキュメンテーションが、遊牧コミュニティの解明のみならず、人類初現の生存戦略とレジリエンス機能を紐解き、出ユーラシア研究に新たな視座を提供できるとの確信を得ることができました。
本年度からの新課題では、「出ユーラシア研究」の要請する「文明形成」のエビデンスに、個別具体の民族誌の提示によって貢献します。「文明」の礎でもある持続型コミュニティの確立に、「草原の伝統知」の継承・実践が果たした役割から、人類の生存戦略を学知融合で探求します。
衛星観測とソーシャルセンシングによる東シベリアの人々の生業の空間分布特徴の検出(海洋研究開発機構・永井信)
本研究の目的は、寒冷地適応の事例研究として、東シベリアのサハ共和国(ロシア)を対象に、民族誌のテキスト情報・景観及び夜間光の衛星観測データ・ソーシャルビッグデータの統合解析という独創的なアプローチにより、河口及び河川からの距離・アラース(当地の特異地形)からの距離といった環境傾度に沿った景観と人々の生業の対応関係の空間分布を解明することである。具体的には、インターネットに接続されたパソコンを主に用いて、(1)衛星観測や気象データの解析により、景観や居住地を地図化し、環境傾度に沿ったそれらの特徴を評価する。(2)ソーシャルビッグデータの解析により、景観の空間分布の特徴と生業についての人々の関心の対応関係を評価する。(3)景観や生業に関わる民族誌情報を収集し、テキストマイニングの手法を用いてそれらの特徴を抽出する。(4)上述(1)から(3)の結果に基づき、環境傾度に沿った景観の空間分布の特徴と生業の対応関係を指標化し、その空間分布を地図化する。
B02班
家畜化によるヒトと動物の関係変容に伴う性格関連遺伝子の変化(京都大学・村山美穂)
人類がユーラシア大陸からアメリカ大陸、日本列島、オセアニアへと移動・拡散したのに伴い、家畜も共に移動した。その際のヒトとの関係性の変化や動物自身の変化は、遺伝的な変化に反映されていると考えられる。本研究では、ユーラシアのオオカミから家畜化された最も古い家畜であり、伴侶動物としてヒトと社会的な絆の深いイヌを中心として、新奇探求性などの移動・拡散に影響する性格の基盤となる遺伝子の多様性を調べ、ヒトの民族や個体間の差違とも比較して、ヒトと動物との相互関係の歴史を遺伝子から紐解き、家畜化に影響したゲノム領域を解明する。具体的には、ヒトの民族間のゲノム差異のある領域について、イヌ品種のゲノムを比較し、差異の大きい候補領域を検出する。候補領域に存在する遺伝子について、イヌ品種間および個体間で、性格等との関連を解析する。性格との関連が見いだされた遺伝子を、ネコや他の家畜など、広範な動物種の間で比較する。
単層・重層社会における集団性と文化形成メカニズムの進化的基盤:比較認知科学的検討(京都大学・山本真也)
人類の出ユーラシアを可能にした「ヒトらしい」行動・心理特性および認知能力の進化的基盤を、比較認知科学の視点から明らかにする。ヒトは、困難な状況に集団で協力して対処する能力に優れている。この集団性こそが、ヒトを人たらしめていると考える。また、集団と集団が団結して協力するというのもヒトの大きな特徴だが、これは複合化社会(重層社会)をもつヒト特有の性質だと考えられてきた。しかし、その進化的起源についてはほとんど解明されていない。申請者はこれまでに、チンパンジーとボノボの協力行動が別々の進化プロセスを経て進化してきた可能性を示唆してきた。また、野生ウマの社会が複合化(重層化)していることも見出した。これらの研究成果を基に、進化の隣人である類人猿とヒト社会の隣人と言える家畜動物を対象とし、彼らがもつ社会性および社会的認知能力を通して、「ヒトらしさ」の進化とその認知メカニズムを明らかにする。
B03班
人類進化に特有なニッチ構築の形跡をエンハンサー領域の単純反復配列から示す(藤田医科大学・嶋田誠)
現代人類の進化はニッチを自ら構築・改変することを特徴する。例えば、高度分業社会を築き、それに適応しつつ、次世代へ引き継いでいることが挙げられる。分業化をもたらす個性の多様化にかかわる現象として、ポリグルタミン病責任反復の多様性(多型)が人類において多様化したことに着目し、その進化の道筋を私は研究している。より直接的にニッチ構築に迫るため、対象を疾患責任反復多型座位から遺伝子発現の量やタイミングを調節する領域の単純配列に拡大することで、「文明形成期」の諸変革を導いたスイッチ的変化をゲノムの痕跡に見出すことを考えている。つまり、人類が構築したニッチである社会環境に関係の深い「脳神経系」と、自然環境の変化に対応する「代謝系」との二種類の遺伝子群に分け、それぞれの調節領域の単純配列において、進化速度の速いSTR反復多型等を両者の間で比較することで、比較的最近人類が人類社会環境へ適応した形跡を明らかにしたい。
頭顔部における硬組織および軟組織形態の共変化とその集団間差異(琉球大学・木村亮介)
顔面形態の集団間の違いは、主に硬組織(骨)の違いを表しているのだろうか、それとも主に軟組織の違いを表しているのだろうか。それを明らかにすることは、顔面形態に働く選択圧を考える上で重要である。これまでの顔面形態の研究において、硬組織形態と軟組織形態を切り分けて表現型を評価する試みは余り多くなく、そのための普遍的な手法も確立されていない。本研究では研究期間内において、①computed tomography(CT)画像を用いて多変量解析および機械学習に基づいた形態解析手法を考案し、軟組織形態に関して硬組織形態に依存する変化と依存しない変化を明らかにしながら、互いに独立な形態形質を新たに定義する。そして、②多変量解析および機械学習に基づいて硬組織形態から顔表面形態を推定する復顔法を提案し、その精度を検証する。さらに、③新たに定義された形態形質において琉球諸島集団および本土日本集団の間の顔面形態の表現型分化を評価する。琉球諸島集団と本土日本集団の違いの一部は、縄文人集団と渡来系弥生人集団の違いに起因すると考えられる。日本列島集団および大陸集団における骨形態の変遷は良く研究されているが、本研究は軟組織形態にどのような変化が起こったのかを理解することに貢献する。
出ユーラシアを支えた寒冷適応:南太平洋の海洋民も寒さに適応したか?(東京大学・中山一大)
ヒトは他の霊長類同様に比較的緯度が低く、気温が高い環境にながらく適応してきた動物である。ヒトが高緯度地域へ進出し、出ユーラシアを果たすことができた背景には、防寒技術の発達に加えて、寒冷環境への遺伝的な適応があったと考えられているが、その実態は明らかになっていない。この研究課題では、出ユーラシアの中継点の一つである東アジアの現代人を対象に、褐色脂肪組織等の熱産生器官の遺伝的多様性を担うゲノム領域を探索するとともに、そこで同定されたゲノム領域に作用した自然選択の痕跡等を解析することによって、出ユーラシアを支えた寒冷適応の遺伝的基盤を解明することを目的としている。2021年度までは、北東アジアを経由した南北アメリカ大陸への進出の際に起きた寒冷適応を標的とした研究を展開した。2022年度からは、それを発展的に継続させるとともに、もう一方の出ユーラシアの舞台となった南太平洋について、果たして海洋環境でも寒冷適応的な進化が起きたのかどうかを明らかにする研究を実施する予定である。
リモートオセアニアへの移住を可能にした遺伝的特性の解明(東京大学・大橋順)
ヒトのオセアニアへの大規模な移住は2回あったと考えられている。最初の移住は、約47000年前に非オーストロネシア語族集団によって行われた。最初の移住により、オーストラリア、ニューギニア、ビスマルク諸島、ソロモン諸島西部からなるニアオセアニアに到達した。2回目は、台湾を起源とするオーストロネシア語族集団の移住であり、彼らは約3500年前にビスマルク諸島でパプア先住民と混血し(ラピタ人の誕生)、ソロモン諸島を経由してリモートオセアニアと呼ばれる、ヴァヌアツ、ニューカレドニア、フィジー、トンガ、サモアへ600年ほどで拡散した。本研究は、ラピタ人の子孫であるオーストロネシア語族集団の全ゲノム配列解析と集団ゲノム学的解析を行い、出ユーラシアを経てリモートオセアニアへ到達したラピタ人の移住・交雑・集団サイズ変化の過程を推定するとともに、彼らが肉眼では確認できない遠方の島への航海を繰り返した遺伝的特性(遺伝的に新奇性追求心が強かったのか)と、それを可能にした遺伝的背景(地域特異的適応変異をもっていたのか)を明らかにする。